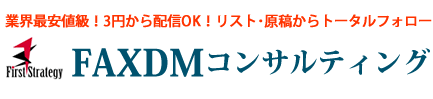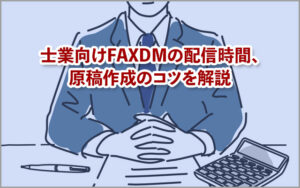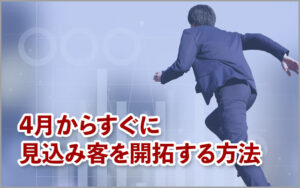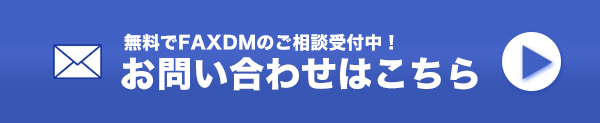教育機関(幼稚園・保育園、小学校、中学校、高等学校)向けFAXDMの配信時間・原稿作成のコツを解説
公開日:2025-08-18 /
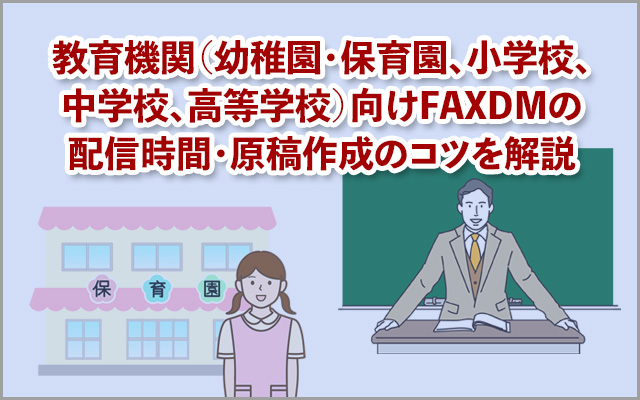
「教育機関にFAXDMを送っても大丈夫なの?」
「そもそも見てもらえるの?」
そんなお悩みはありませんか?
この記事では、保育園・幼稚園、小学校、中学校、高等学校といった各教育機関の特性に触れながら、FAXDM配信のタイミングや原稿作成のポイントを丁寧に解説します。
教育機関にFAXDMを初めて送る方でも安心して取り組めるよう、注意点や成功の秘訣もまとめました。
最後まで読んでいただくと、
「FAXDMを送って迷惑がられないか不安…」
といったお悩みが解消でき、初めての方でも反応率を高めるFAXDMを作れるようになります。
目次
教育機関への営業活動にFAXDMは適している?
教育機関では、現在も「紙の書類」や「掲示物」を使った情報共有が主流です。特に保育園や幼稚園では、デジタル化が十分に進んでいない施設も多く、FAXは今なお日常的な連絡手段として活用されています。
また、小学校・中学校・高等学校においても、教職員が日中にスマートフォンやメールを確認する時間は限られています。そのため、紙で届くFAXは目に留まりやすく、情報伝達手段として有効です。
一方で、教育現場は常に多忙なため、電話営業やWeb広告といった即時対応が求められる手法は、反応を得にくい傾向があります。
こうした背景から、FAXDMは教育機関に情報を確実に届けやすい手段として、今でも高い効果が期待できます。
しかしながら、公立校と私立校ではFAXDMの取り扱いが異なります。
公立校では、教務主任や事務職員がFAXを確認することが多いです。宛先が明記されていれば良いのですが、宛先不明で商業色が強いFAXは拒否されてしまいます。中には、園長・校長の判断で営業FAXを一括拒否していることもあります。
また、教材や設備の導入などは学校単位ではなく、教育委員会や市区町村で決定されることがほとんどです。内容によっては、FAXDMで公立校に直接アプローチしても、反響につながらない可能性があることは、事前に押さえておきましょう。
一方、私立校では公立校と比較すると、裁量権が大きいので意思決定が早いです。場合によっては配信したその日に反響が獲得できることもあります。
教育機関向けFAXDMで反響率を上げるための3ステップ
FAXDMでお問い合わせを獲得するには事前準備が大切です。配信しようと決めたら、まずは以下の3つを明確にしましょう。
ステップ1:リストの見直しをする
まずは、貴社で保有しているリストを見直しておきましょう。「いつ更新したのかわからない」などの不安がある場合は、リストの購入を検討するのもおすすめです。
※弊社のリストをレンタルして配信いただくことも可能です。お気軽にご相談ください。
リストのレンタルについて相談する
ステップ2:どんな案内を送るかを明確にする
次に、FAXを配信する目的をはっきり決めましょう。目的が曖昧なまま配信するとFAXの内容がぼやけてしまい、読み手に全くささりません。
教育機関向けのFAXDMで受け入れられやすいのは、以下のようなご案内です。
- 教材や教育関係者向けの研修・講演、進路指導支援など、教育的意義が強いご案内
- 学校運営への貢献をサポートするご案内
一方、物販や営利色が強い商材は特に敬遠されやすい傾向があります。学校運営等にどれだけ必要かを原稿内でしっかり伝えないと、反響はなかなか獲得できません。
また、複数の目的をFAXDMで達成しようとすると、それぞれの内容が中途半端になって読み手の心にささらず、反響獲得は非常に難しいです。
1つのDMに対して、目的は必ず1つに絞ることを徹底しましょう。以下は例の一部です。
- 研修や講座の案内
- 資料送付の許可取り
- 担当者との面談調整 など
ステップ3:問い合わせ導線を設計する
お問い合わせ方法はFAXを前提にして、DMを作成しましょう。
FAXDM最大の特徴は「受け取ったFAXに記入してそのまま返せる」ことです。実際に、お問い合わせの8割は届いたFAXをそのまま返信しています。
なお、業務中にスマートフォンを使えないことが多いため、二次元バーコードよりも、パソコンからアクセスできるような問い合わせフォームを用意できると親切です。その際、短縮URLを掲載するなど、できるだけ受け手の手間を減らす工夫をしましょう。
※貴社にFAX機がない場合、弊社ではFAX一次受付のサービス(有料)がございます。サービス内容は以下のボタンから確認できます。
『FAX一次受付』のサービス内容を確認する
教育機関向けFAXDMの配信でおすすめの時間帯と曜日
事前準備ができたら、次は配信のタイミングを検討しましょう。配信のタイミングは反響を左右する重要な要素です。
業務スケジュールや教職員の行動パターンを踏まえると、以下の時間帯・曜日が最適と考えられます。
おすすめの時間帯
教育機関では1日のスケジュールが大体決まっているため、FAXを確認できる時間帯は限られます。見てもらいやすいタイミングを調べて、配信しましょう。
保育園・幼稚園の場合
保育園・幼稚園は常に多忙ですので、FAXを確認できる時間帯は限られます。配信時間は、午後2時から3時半ごろがおすすめです。午後の事務作業や休憩のタイミングでFAXを見る余裕が生まれやすいからです。
小学校・中学校・高等学校の場合
保育園・幼稚園と比較すると、配信タイミングは複数あります。
- 11:00〜13:00(昼休み前後):教職員が職員室や教科ごとの教員室に戻るので、FAXを目に留めてもらいやすい時間帯です。事務職員も対応しやすく、受信をチェックする余裕もあります。
- 16:30〜17:30(放課後〜退勤前):授業が終わり、部活動や校務を行う時間帯です。FAXのチェックも後回しにされにくく、読んでもらえる可能性が高まります。
おすすめの曜日
平日中盤の火曜・水曜・木曜がおすすめです。園の事務作業や学校業務が比較的安定しているので、FAXを確認してもらいやすくなります。
ただし、この曜日が祝日となっている場合は、配信を避けましょう。祝日は公立・私立ともに原則休校で、事務室や職員室にも教職員が不在のことがほとんどだからです。FAXを送っても確認まで時間がかかったり、他のFAXに埋もれて見落とされたりする傾向があります。
教育機関への配信を避けるべき時間帯と曜日
一方で、避けるべきタイミングもあります。FAXDMは目にとめてもらえなければ反響を獲得できません。
避けるべき時間帯
FAXDMを避けた方が良い時間帯は以下の通りです。
保育園・幼稚園の場合
先ほど説明したおすすめの時間帯以外になりますが、なぜ避けるべきかを解説します。
- 午前中:登園対応や朝礼のほか、体操や製作・音楽などの活動があります。事務所も現場も非常に忙しいので、ほとんど見てもらえません。
- 午後3時半以降:特に保育園では降園準備が始まり、再び慌ただしくなります。職員も順次退勤準備を始めるため、後回しにされやすいです。
小学校・中学校・高等学校の場合
1日のスケジュールが大体決まっているため、「後回しにされやすいかどうか」で判断するのが基本です。
- 早朝(9時前):朝の職員会議や授業準備などで忙しい時間帯です。FAXを見る余裕はほとんどありません。
- 17:30以降:学校に残っている先生がいても、部活動やその日のうちに対応すべき業務に追われていて、FAXは後回しにされやすい傾向があります。
避けるべき曜日
避けるべき曜日に関しては、すべての教育機関で共通となっています。
- 月曜:週の始まりは会議や事務作業などで忙しく、FAXの確認は後回しになりがちです。
- 金曜:週末の業務に追われていることが多く、FAXが手元にあっても確認が翌週にまわされる傾向があります。
教育機関向けFAXDM原稿作成の5つのポイント
「後回しにされない」という一つのハードルをクリアした後は、FAXを読んでもらえるかどうかというハードルが待っています。
これを超えるためには、FAX原稿に工夫が必要です。
今回はその中でも特に注目していただきたい5つのポイントを説明します。
ポイント1:読み手の悩みに寄り添ったタイトルをつける
タイトルをひと目見ただけで「これはうちに必要ない」と判断されると、そのまま破棄されてしまいます。そのため、タイトルで「うちに関係のある案内だ」と感じてもらうことが最優先です。
具体的には、読み手が抱えている課題に寄り添った内容がおすすめです。抽象的な言葉を使ったメッセージ性の高い文章や、広告などでよく目にするような言葉を使っても、読み手の目には止まりません。「何の案内か」「園(学校)にどんなメリットがあるのか」を簡潔にまとめることを意識しましょう。
ポイント2:校務の負担軽減や教育効果に直結するベネフィットを提示する
FAXDMで反響を獲得するには、商材などを説明するだけではなく、ベネフィットを示すことが重要です。
ベネフィットとは「その商品・サービスを利用して得られるうれしい結果や変化、メリット」を指します。このベネフィットを原稿で示すことができなければ、必要性を感じてもらえません。
例えば、業務効率が期待できるサービスであれば
- 準備が簡単なので、導入したその日にすぐ利用できる
- 新たな機器を購入する必要がないので、費用がかからない
- これまで●時間はかかっていた業務が、たった20分でできるようになった など
のように、「どんな嬉しい結果につながるのか」「何がどう変わるのか」を、数字などを用いてできるだけ具体的に示しましょう。
また、教材やイベント、進路支援であれば、
- 授業で使えるプリントが100種類あるので、準備に時間がかからない
- 保護者も一緒に参加できるので、家庭では分からない子どもの様子を知れる
- 生徒自身で考え、表現し、まとめる力が身につくので、大学進学や就職活動に役立つ
- 進路面談・三者面談の資料にも使えるので、保護者とのコミュニケーションが円滑になる など
のように、教職員や児童、生徒だけでなく、保護者の立場からも「うれしい」と思えるポイントを押さえましょう。
ポイント3:読みやすいレイアウトにし、簡潔にまとめる
FAXDMは業務の合間に目を通すものです。そのため、長々と説明文を記載しても読み飛ばされてしまうことがほとんどです。
箇条書きにしたり、太字や下線で強調したりするなど、読みやすさを心がけましょう。
なお、FAX機において画質の解像度は低めなので、原稿に掲載した画像は粗く印刷されます。また、パンフレットなどに掲載している図を FAX原稿に掲載しても、文字が潰れてほとんど読めません。
読めない箇所があるFAXは、その場で破棄されやすいです。何よりも、読み手に価値が伝わりません。「情報が欠けている」「配信前に確認していないのか?」と、貴社への印象がマイナスになる恐れもあります。
そのため、シンプルな構成にして、A4サイズ1枚に収めることを意識しましょう。以下の構成でFAXDMを作成すると、読み手に要点や魅力が伝わりやすいです。
- キャッチコピー
- 自己紹介とFAXに至ったきっかけ
- 今回ご案内するものの特徴・メリット
- 導入実績
- 行動喚起
ポイント4:導入実績や実際に導入した声を具体的に掲載する
商材・サービスの特徴を説明しても、それが必要だと判断できる材料がなければ、お問い合わせにはつながりません。
例えば「全国の保育園・幼稚園の●園で導入」「教員の94.7%が業務時間の短縮を実感」「教育業界紙にも掲載」など、意思決定を後押しする具体的な根拠を記載しましょう。その際、お客様の声として事例を掲載できると、導入後の変化がイメージしやすくなるのでおすすめです。
また、導入実績だけでなく、第三者の声やメディア紹介実績なども判断材料となります。できる限り記載しましょう。
ポイント5:“今すぐ行動したくなる”オファーを提示する
「あとで検討しよう」と思われたFAXは、そのまま忘れられてしまうことがほとんどです。後回しにされないよう、オファーを必ず用意しましょう。具体的には、実際に導入する前にお試しや教材の一部確認ができるといった、“実際に触れられる”ものがおすすめです。
その際、期限やお申し込み数などを限定することで、行動の後押しになります。どんなに魅力的なオファーでも、限定性がないとお問い合わせにはつながりません。
以下の例をもとに、限定性も添えましょう。
- 先着10校様限定で、1回分の教材+指導案セットを無料でお送りします
- 本日から○日以内にお問い合わせいただいた方は、7日間無料でお試しできます など
教育機関向けFAXDM原稿で注意すべきこと
原稿を作るときには、できるだけ避けた方が良いこともあります。その中でも注意が必要すべき点を3つお伝えします。
注意点1:売り込み感を出さない
教育機関では、強い営業色のあるFAXは迷惑だと思われやすいです。営利目的が前面に出た内容だと、読まずにすぐ廃棄されてしまう可能性もあります。
商材・サービスに自信を持つことは良いのですが、学校の課題に寄り添う姿勢を忘れないようにしましょう。「指導に役立つ情報の提供」や「校務を支援」など、学校で抱えている課題やお悩みの解決につながる方法を提案する、という姿勢が大切です。
注意点2:ターゲットを1名に絞り、その人に向けて作成する
小中学校のように全教員が1つの職員室に常駐するケースもあれば、高等学校では「教科ごとの教員室(分掌室)」が設けられています。そのため、FAXDMの左上に宛先を明記しましょう。
その際、宛先は園内あるいは校内のたった1名に絞ることが非常に大切です。複数記載されていると、誰に渡すべきか迷ってしまうからです。以下の例を参考に具体的に記載して、読み手の手元に確実に届くようにしましょう。
- 園長先生へ
- 進路指導責任者様
- 探究学習担当者様 など
注意点3:送信元の情報を掲載し、信頼性を高める
教育機関はとくに怪しい業者を警戒しています。「FAXの送信元の企業は信頼できるところかどうか」を非常に重視しているので、企業情報が明確に掲載しましょう。
せっかくFAXの内容に興味を持ってもらえても、会社情報が不十分だと不安になったり怪しまれたりして、お問い合わせを躊躇される傾向があります。
会社情報などの連絡先はもちろんですが、貴社の実績やメディア紹介実績など信頼につながる情報はできる限り記載しましょう。
弊社では、FAXDMテンプレートをご用意しています。累計10,000件以上の原稿アドバイスを行なってきた弊社オリジナルのものです。
テンプレートをダウンロードいただくには、会員登録が必要です。貴社名とメールアドレスをご登録いただければ、すぐにご利用いただけます。
なお、費用は一切かかりませんので、この機会にぜひご活用ください。
まとめ:配信タイミングと内容を工夫して“問い合わせしたくなるFAX”を届けましょう
FAXDMで反響を獲得できるかどうかは、「目的を明確にすること」「読んでもらえる時間に届けること」で決まります。
教育機関からFAXDMの反響が得られるかどうか不安に思う方は多いのですが、読み手が「これはうちに必要だ」と価値を感じるFAXなら、お問い合わせしてくれます。こちらが伝えたいことを一方的に紹介するのではなく、相手の課題に寄り添う姿勢が成功への近道です。
本記事を参考に「問い合わせたくなるFAX」を届けましょう。